こんにちは!づっきーです。
引きこもり始めてから、やることがなくてこれまで以上に色んなことを考えるようになったので、
蓋をしていた過去の記憶たちが徐々に表出(ひょうしゅつ)し始めています。
そこで今日は、づっきーの小学校の歴代担任の先生方について思い出したので、
その先生方の簡単な特徴と、づっきーがその先生方に対して抱いていた思いについて語っていきたいと思います。
それでは、今日も最後までよろしくお願いいたします。
小学校の担任
正直、中学校までの記憶はほぼなくて、というよりは、思い出さないように必死に封印してきたので、
今更思い出すなんて、自分でも考えもしませんでした。
だからこそ、また忘れてしまわないうちに、ここに書き留めておこうと思いました。
1年生
1年生の時の担任は、F先生(※プライバシーの観点からイニシャルで書きます。)という方で、
定年間近だったため、づっきーのクラスが、彼女にとって最後の年だったような気がします。
パワフルで厳しくて、定年近いとは思えないほど元気な先生でした。
しかし、その厳しさ故に、F先生に対して苦手意識を持っている生徒も多かった印象があります。
一方で、づっきーはというと、F先生が割と好きでした。
とても厳しいけれど、その分、ちゃんと生徒一人一人を見ていて、本当に愛のある先生でした。
小学1年生=6歳ながら、生意気にもそんなふうに捉えていました。
づっきーは、その頃から既に仲間意識や友達作りが苦手だったため、
学校に行くのが本当に怖くて、嫌で嫌で仕方ありませんでした。
そんなづっきーをF先生は、厳しくも愛のある形で学校という社会への仲間入りを後押ししてくださったと思っています。
現在もご存命かは定かではありませんが、
1年生でF先生に出会えたことに感謝しています。
2年生
2年生の時の担任の先生は、F先生とは真逆にも近いほど、
優しくて朗らかとしていて丸っこい印象の、Y先生という方でした。
Y先生はいつも耳に赤鉛筆をかけていて、
づっきーは、Y先生がその赤鉛筆の紐をピーッと伸ばして芯を出しているのをみるのが好きでした。
紐を引っ張ると、なぜか芯の周りの部分がくるくるっと薄く剥がれて、芯が出てくるのです。
どんな仕組みなのか、当時はとても不思議でした。
あと、耳の中に毛が生えている人もいるんだな、と知ったのもY先生のおかげです。(笑)
正直なところ、小学校の頃の担任の先生方について振り返ってみる!とか言っておいて何ですが、
あまりよく覚えていません。
Y先生のことも、とても優しくて、学校が苦手だったづっきーを全面的に受け入れてくれた、
ような気がする、という程度です。
なんというか、1年生と2年生で、飴と鞭みたいな構造ですね。
3年生
3年生の時の担任は、M先生で、これまた少し厳しめの先生でした。
づっきーが通っていた小学校は北海道の中でも2番目?(諸説あり)に古い学校で、
黒田清隆によって命名されたとかなんとか、とにかく校舎からしてものすごく古い学校だったためか、
厳しめの先生が多かったのかもしれません。
それはさておき、M先生には、実は苦い思い出があります。
とある図工の授業で、づっきーのクラスは紐を引っ張ると走り出す車のようなものを作っていました。
評価基準は、紐を引っ張って何メートルか真っ直ぐに走るほど、評価がよくなるというものでした。
づっきーはそこまで手先が器用ではなかった上に、理解力が乏しかったので、かなり苦戦していたのを覚えています。
勉強は常に学年でトップにいるほどできるのに、理解力は低い
これはずっと変わらないままです。
それでも、なんとか作り上げて、いざ走らせてみると、
みんなみたいには綺麗に真っ直ぐは走らなかったものの、数メートルは走りました。
嬉しくてたまりませんでした。
しかし、M先生はなかなかに厳しく、づっきーが作った車は走ったことにはならない、
と言われてしまいました。
完璧主義的な部分を持つづっきーの自尊心は、一瞬で打ち砕かれました。
その日以来、づっきーはまた学校が嫌いになりました。
そして、「先生」という存在に疑問を持ち始めました。
4年生
4年生の時は確か、I先生という方で、
お腹が風船のようにまんまる、という第一印象を誰もが持ちそうな先生でした。
そんな柔らかい見た目の割に、と言ったら差別/偏見になってしまうかもしれませんが、
I先生は、一度お説教を始めると授業なんてお構いなく、1時間でも2時間でも、
生徒が反省するまで、もしくは自分が満足するまで延々と起こり続ける先生でした。
実はこのI先生は以前、づっきーの姉の担任も持っていたため、そのことは知ってはいたのですが、
あんなにも頻繁に、だらだらと続くお説教があるなんて思いもしませんでした。
あのお説教の分の授業をどうやって取り戻していたのか、今でもそのメカニックを理解できません。
あそこまでする必要があったのかは分かりませんが、小学校の高学年になったタイミングで
悪いことをしたらあんな嫌味ったらしいお説教が待っている、という社会勉強をするには良かった、
と言えるかもしれません。(百歩譲りましたが。笑)
とはいえ、成績と姉の存在のおかげもあって、づっきーは”良い生徒”として見られていたため、
目をつけられるどころか、づっきーに対しての待遇はかなり良かったです。
当時のづっきーは、友人に裏切られたと思ったらすぐに悪口を言ってしまうような”悪い生徒”だったのですが。
八方美人とはこのような人のことを言うのかもしれませんね。
表向きには、勉強に勤(いそ)しみ、好成績をとり、好印象を持たせる
一方で、裏ではコソコソと人の悪口やゴシップを言いふらしている
本当にどうしようもない生徒ですね、づっきーは。
5,6年生
5,6年生は同じ先生だったはずです。(違ったら陳謝します。笑)
顔は出てくるのに、名前がどうしても思い出せませんでしたが、
づっきーはその先生がかなり苦手でした。
というのも、その先生はなんというか、かなりぶりっ子気質で、
自分の好きな生徒と嫌いな生徒に対する対応をあからさまに変えていたからです。
少しでも、「あ、この子は成績も思わしくないし、あまり”良い生徒”ではない」と判断したら、
その子に対してみんなの前で怒る、という公開処刑的措置を取る先生でした。
そして、その先生も自分の気が済むまでお説教をやめない人でした。
まあ、何時間コースっていうことはありませんでしたが。笑
一方で、作っているものとはわかっていたものの、
普段はとても穏やかで、接しやすい先生という印象もありました。
恐らくづっきーは嫌われてはいなかったと思いますし。
なんせ、その先生の好きな生徒と仲良くしていたので。
ただ、3年生の時の担任に感じた「先生」という存在に対する違和感や疑問が増したのも、
この先生がきっかけです。
「先生」という存在
づっきーはそれまで、先生=生徒の模範となる存在、であると考えていました。
しかし、その模範的存在が言っていることとやっていることが矛盾していることも多かったのです。
うまく言葉では表せませんが、先生が先生という立場を利用して、
生徒が”悪口”として行なっている行為を、”説教”という暗黙の了解として、行使しているように見えたのです。
先生になれば、公開的に、自信と共に、その人を否定しても許されてしまう。
なぜなら、生徒にとって先生とは模範的存在だからです。
勿論、生徒が別の生徒に向かって、堂々と悪口を言ったとしても、それは悪口以上の何にもならず、
その行為は”悪い行い”としてみなされます。
そして、その”悪い行い”をした生徒は先生によって、説教という形で罰せられます。
しかし、その説教の中に、先生によるその生徒への偏見が入っていないと言い切れるでしょうか。
づっきーは小学生の頃、幼ながらにそんなことを考えていました。
そして現在もなお、考え続けています。
なぜなら、答えは1つではないから。もしかすると、答えはないのかもしれないから。
答えのある問題を解いていくのもスッキリしますが、
答えのない課題について永遠に解い続けていくのも非常に興味深いものです。
ここまで読んでこられた皆さんも、一度、見えなくて答えを導き出せそうにない何かについて
考えてみてはいかがでしょうか。
それでは、今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました:))
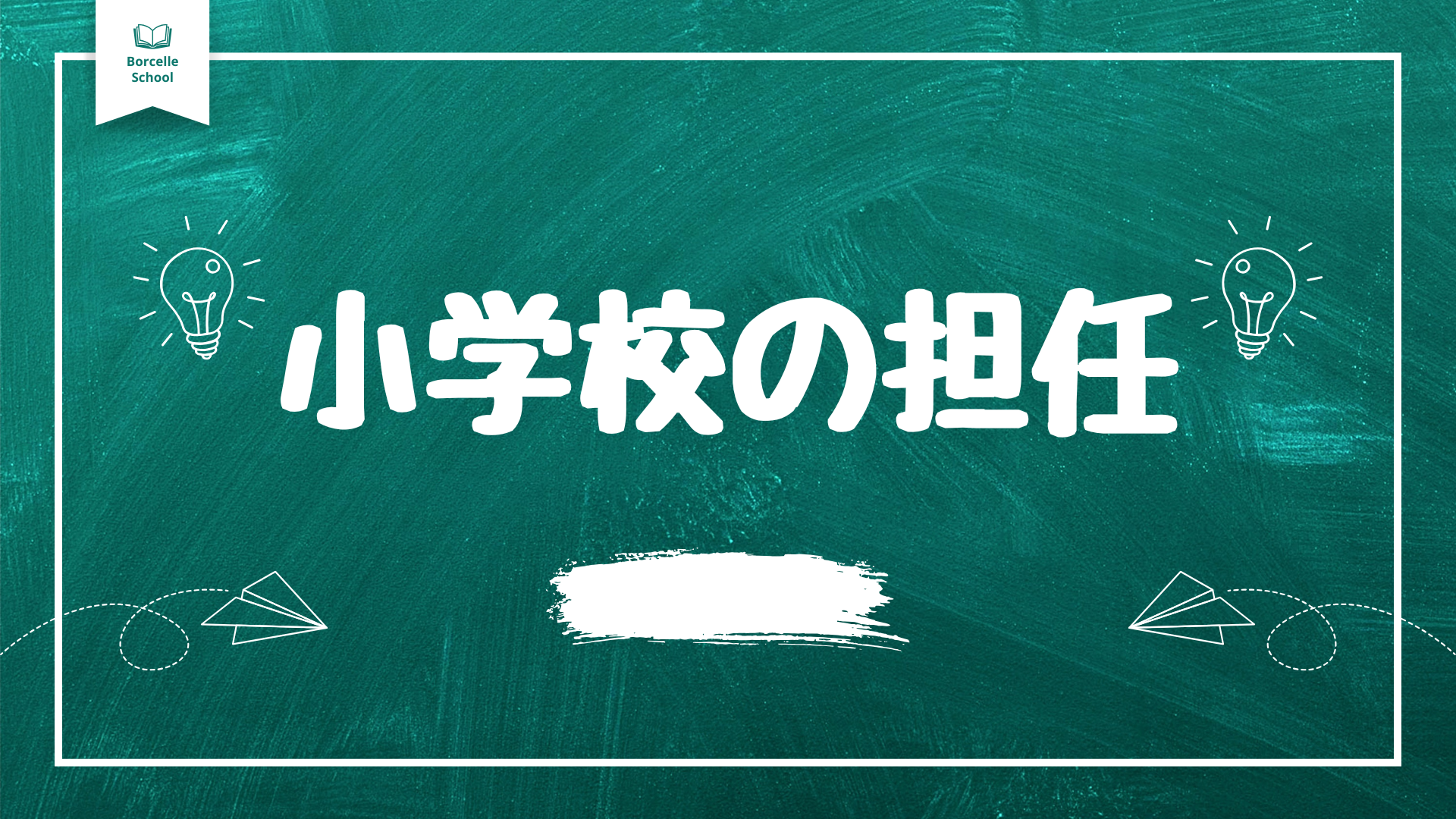
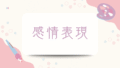
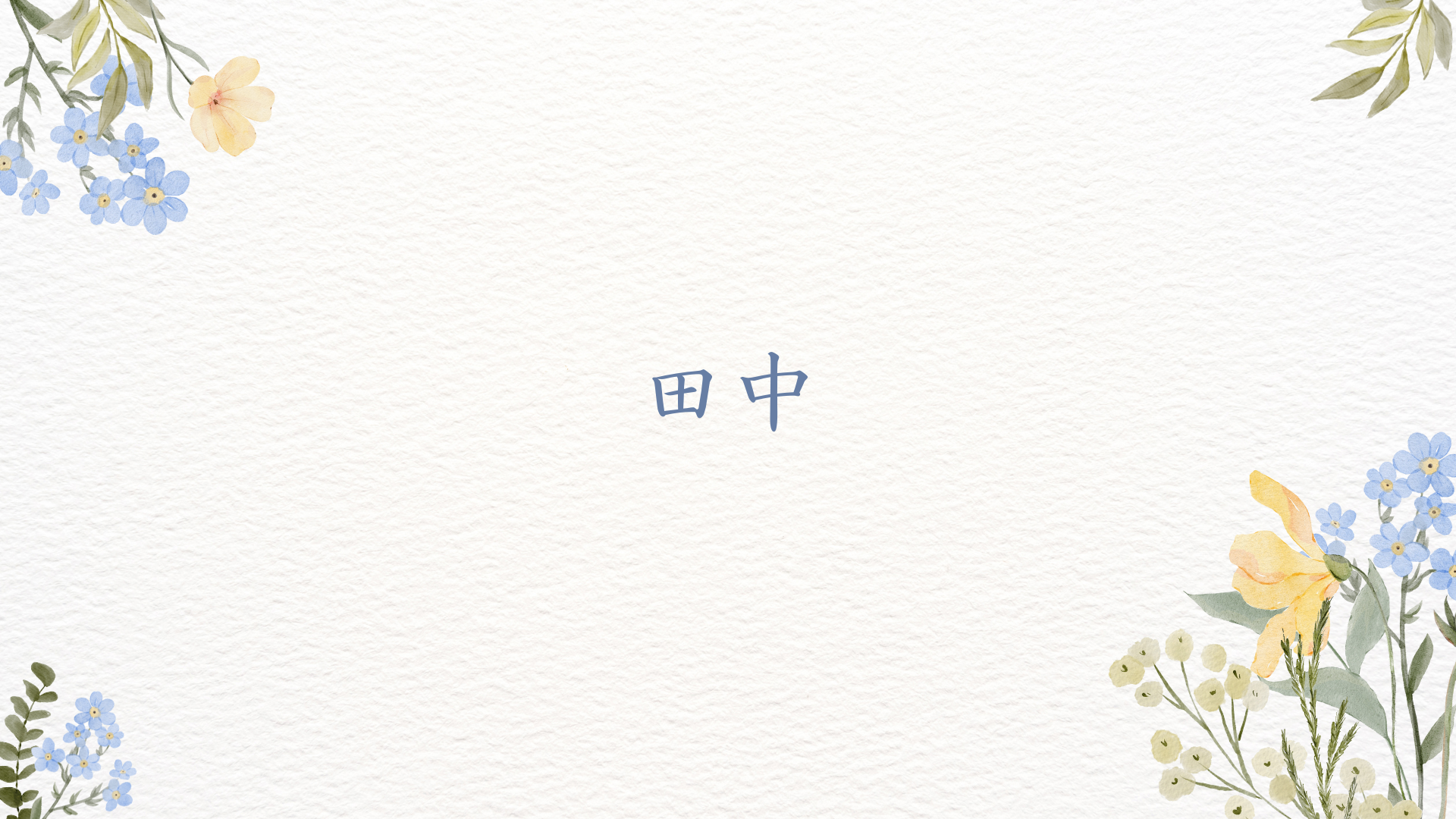
コメント